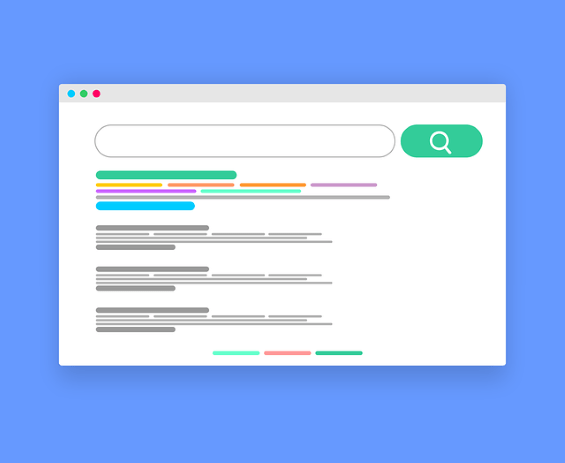LPOとは何?SEO・EFOとの違いをわかりやすく解説
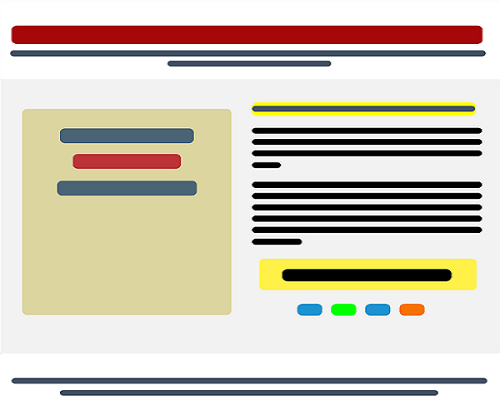
「LPOとは一体どういったものか」
企業のマーケティング担当者の中には、一度は聞いたことがあっても、詳しい意味までは分からずお困りの方もいらっしゃいます。
特に、導入を検討している方はLPOのことに関して熟知しておくべきです。そこで、今回はLPOについて解説します。
この記事を読めば、導入メリットだけでなくSEO・EFOとの違いもわかるようになります。
LPO対策の効果的な手順も紹介していますので、自社の売り上げアップのためにCV率や広告の費用対効果を高めたい方は、ぜひご覧ください。
LPOとは?

LPO(Landing Page Optimization)とは、「商品やサービスに関する問い合わせや資料請求の件数(コンバージョン)を増やすために、ランディングページを顧客にとって使いやすいものに改善すること」です。
誕生したのは1996年で、最初の10年は存在があまり知られていませんでした。ところが、2006年にGoogleによってツールが提供され始めてから認知度が格段にアップしました。
それ以来、顧客による衝動買いを意図的に増やしたいと考える多くの企業で導入されています。
そんなLPOは、ランディングページの成果を最大化させる役割を担うため、「ランディングページ最適化」という呼ばれ方をすることもあります。
最適化されていないランディングページは、ボタンの配置やデザインが微妙であったり、表示速度が遅かったりと、とても顧客のことを思って作られたページとは言えません。
そのため、ユーザーがやってきたとしてもなかなか定着せず、コンバージョンにも繋げられません。
しかし、最適化させたランディングページであれば、どうでしょう?適切な位置におしゃれなデザインのボタンが設置されているページは、ユーザーの目には魅力的に映ります。
時には、広告や検索結果をクリックしてやってきた通りすがりのユーザーでさえも、たちまち引き寄せられるほどです。
これで、ランディングページを途中で離脱するユーザーの数も一気に減ることでしょう。そのうえ、自社の宣伝ページともいえるランディングページにユーザーを囲い込むことができれば、コンバージョン増加を期待できます。
このようにLPOは、コンバージョン数やCVR(成約率)の増加、広告の費用対効果アップといった可能性を秘めており、最終的には売上アップにも繋がると言われているほどです。
ランディングページ(LP)の定義

ランディングページ(Landing Page)通称LPには、「広い意味でのLP」と「狭い意味でのLP」2つの意味があります。
広い意味でのLPとは、「広告や検索結果のクリックによって遷移してきたユーザーが最初に閲覧するWebページ全般のこと」です。
一方、狭い意味でのLPとは、「1ページで構成された縦長の広告ページのこと」です。
企業などが商品購入や資料請求、お問い合わせといったユーザーからのコンバージョンを増やすことを目的として作ります。いわば、初めからコンバージョン獲得を想定した広告ページと言えるでしょう。
このようにランディングページは、ユーザーが初めに閲覧したWebページを指すこともあります(広義)が、実際には縦長の広告ページという意味で使われる(狭義)ことも少なくありません。
ちなみに、「着陸する」を意味するランディングという言葉が使われているのは、ユーザーがWebページに着陸しているためです。
そんなランディングページには、「購入ボタン」「申し込み」「問い合わせ」といったCTAボタンが設置されています。
設置する際は、せっかくやってきたユーザーを離脱させないために、配置やデザインに顧客がついクリックしたくなるような仕掛けを施すことが大切です。
上手くいけば、ユーザーの直帰率(離脱率)減少やCV率の向上を期待できます。
CVを増やしたいが、まだランディングページを作っていないという方は、これを機にランディングページを導入してみてはいかがでしょうか。
ユーザーの心を打つような出来に仕上げられれば、資料請求の件数や会員登録を増やせるかもしれません。
コンテンツマーケティングって、どんなマーケティング手法のこと?
LPO導入のメリット

LPO導入には、次のようなメリットがあります。
・広告の費用対効果を高精度に分析できる
・顧客満足度が向上する
以下では、詳しく解説します。
広告の費用対効果を高精度に分析できる
従来、広告の効果を測るための手法として電話・ダイレクトメール・テレビ・雑誌・直接訪問が主流でした。
しかし、これらの方法では検証に時間や費用がかかるなど幾つか問題点がありました。そこで登場したのがLPOです。
LPOを導入して成果を測定すると、無駄な費用や手間を抑えられます。それだけでなく、次のような効果も期待できます。
・ユーザーの属性がわかる
・ユーザーがどこから流入してきたのかがわかる
・クリック率やコンバージョン率といった数値的なデータを得られる
・媒体・出稿先ごとに費用対効果を分析できる
今までもより、高いレベルで広告の効果を測定したいお考えの方は、LPOを活用してみてはいかがでしょうか。
顧客満足度が向上する
LPOを導入すると、顧客の満足度が向上するとされているのは、ランディングページが最適かされていると、ユーザーが操作や閲覧をしやすくなるためです。
最適化されたランディングページは、ユーザーにとっての使いやすさを徹底的に追求したものであり、顧客に寄り添っています。それゆえ、多くのユーザーから愛されます。
たとえば、いま目の前に「読み込みのスピードが速いページ」と「読み込みに時間のかかるページ」があるとします。
このとき、顧客に喜んでもらえるのは一体どちらのページでしょうか?もちろん前者の速いページでしょう。
このようにランディングページは、ユーザーに「使いやすい」と感じてもらえれば、顧客の満足度を高められます。
ユーザーがいつ広告や検索結果から遷移してきても対応できるように、常日頃より顧客を第一に考えたページづくりを済ませておくことが大切です。
LPOとSEO、EFOの違い

LPO・SEO・EFOは、どれもアルファベット3文字で字面が似通っていることもあり、間違われやすいですが、意味が異なります。
そこで、この節ではLPOとSEO・EFOの違いをそれぞれ解説します。
LPOとSEOの違い
LPOとSEOは名前や働きが少し似ているため混同されやすいですが、意味が異なります。
どちらもCV数アップのために行われますが、コンバージョンの増やし方が異なります。
SEO(Search Engine Optimization)とは、「特定のWebサイトを検索順位の上位に表示させるために行なう施策」です。
検索エンジン最適化とも言い、実施することでサイトへの検索流入の増加を見込めます。
SEOが膨大な量のページからなるサイト全体を検索エンジンが高く評価しそうな形に仕上げることでユーザーを集客するのに対し、LPOはランディングページという1枚のページの質を改善することで、離脱するユーザーを減らし、コンバージョン増加をさせます。
この話を聞くとLPOにもSEO効果がありそうに思えますが、実はないのでご注意ください。
なぜなら、企業側からの一方的な情報にも見えてしまうLPOは、Googleからユーザーの検索意図を考慮したページとはみなされず、評価されないためです。
このように、LPOとSEOはアプローチこそ違うものの、「CV数アップを期待できる」という点で働きが似ています。
コンバージョンを増やしたい方は、その効果を最大化させるためにも、LPOとSEOを同時進行で行なうことをおすすめします。
LPOとEFOの違い
EFOも名前が似ているためLPOと混同されやすいですが、少し意味が異なります。
EFO(Entry Form Optimization)とは、「入力フォームを改善してCVに繋げる施策のこと」で、エントリーフォーム最適化とも言います。その働きからもわかるように、LPOの一部と思ってもらって構いません。
ただ、LPOがEFOを内包しているだけで、まったく同じものでもなく、もちろん相違点もあるのでご注意ください。
両者の違いは、「改善する範囲」と言えるでしょう。LPOがファーストビューやCTAボタン、外部リンク、コンテンツ、ページの読み込み速度など、改善する範囲が広いのに対し、EFOは入力フォームだけです。
とはいえ、ページをユーザーにとって使いやすいものにするためにEFOは欠かせません。
なぜなら、ランディングページが良かったとしても、入力フォームが使いづらければ、ユーザーが途中で離脱し、CVへ繋がらなくなってしまうためです。
入力フォームを改善する際は、必須の項目を目立たせ、不要な項目は削るようにしましょう。
せっかくの顧客獲得のチャンスを逃してしまわないためにも、LPOと併せて行なうべきだと言えます。
お問い合わせフォームからユーザーの離脱を防ぐEFO対策とは?
LPOが向いているパターン
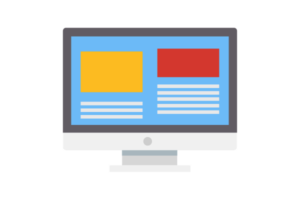
LPOは、売り上げアップといった目標を達成したいケースに向いています。
昨今LPOがWebマーケティングの分野で活用されているのも、ランディングページが次のような特徴を持っているからに他なりません。
・レイアウトで縦長で、情報量が多い
・リンクが少なく、ユーザーの離脱を防げる
・デザイン性の高く、インパクトがあるため、見ていて飽きない
このようにランディングページは、ユーザーがあれこれ考えすぎないように設計されています。
だからこそ、数多くのユーザーをコンバージョンに誘導することに成功しているのです。
LPO対策が効果的な手順

では、LPO対策をするにはどうすれば良いのでしょうか?
LPOを行なう時は、次の5つの手順を踏む必要があります。
・目的の明確化とKPIの設定
・現状の課題を明らかにする
・具体的な施策を決める
・施策を実施する
・効果測定を行なう
以下では、詳しく解説します。
目的の明確化とKPIの設定
LPO対策をする際は、まず「何のためにランディングページ最適化を行なうのか」をはっきりさせておく必要があります。
そのうえで、成果を測る指標としてクリック数やコンバージョン数といったKPIを設定しなければなりません。
なぜなら、数値を使って分析すれば、「最初に掲げた目標のうち、どこまで達成できたか」が一目見てわかるためです。
たとえば、新しくオープンする予定の喫茶店の場合、お店を宣伝する材料としてランディングページを制作しますが、その際まず「売上を上げる」という目標を掲げるでしょう。
そして次に、その目標を達成するために必要な指標として1日の「予約数」や「来店数」といったKPIを設定するはずです。
現状の課題を明らかにする
LPO対策は、最初の段階で目的とKPIを決めますが、もちろんこの時点では成果を上げるにはまだ不十分と言えます。
なぜなら、「自社に何が足りないのか」「コンバージョンが増えない原因となっているのは何か」が把握できていないためです。
たとえば、先ほど例に挙げた飲食店のケースではどうでしょうか?
「予約数」や「来店数」は達成できていても、「キャンセル率」が高いといった問題が生じる恐れがあります。
こうした場合、何がいけないのでしょうか?問題を洗い出してみると、次のような可能性が考えられます。
・味が良くない
・価格が高い
・回転率が良くない
・口コミが良くない
・競合他社に顧客が流れている
こうした現状の課題の把握には、Googleアナリティクスなどのツールが効果的ですので、LPO対策の一環で現状の課題を明らかにする際に活用してみてはいかがでしょうか。
具体的な施策を決める
自社が抱えている問題点があきらかになったら、次は改善に向けた具体的な施策を決める段階です。同じく先ほどのケースでは、次のような施策が有効と言えるでしょう。
・試作を繰り返し、味の研究を重ねる
・価格を見直す
・提供時間を早めるなどして回転率を上げる
・好評な口コミをしてもらえるように快い接客を心掛ける
・顧客が流れないようにする(期間限定キャンペーン実施やクーポン券配布など)
施策を実施する
施策の中身が決まれば、いよいよ実施の段階です。
このとき、注意しておきたいのは、目標を見失わないことです。
問題点を改善することももちろん大切ですが、「何のために課題を改善しようとしているのか」立ち返ってみると良いかもしれません。
飲食店への集客の例でいうと、途中で出てくる「価格の見直し」や「回転率のアップ」といった施策は、あくまでも売り上げを大きく左右する「キャンセル率」を下げるための試みであり、本来の目標は「売上を上げること」なのです。
効果測定を行なう
施策を実施したら、最後に効果測定を行ないましょう。
LPOでは、施策を実行する前後を比べる必要があります。それも1度や2度ではなく定期的に行わなければなりません。
なぜなら、「制作→分析→改善→検証→最適化」といった具合にPDCAのサイクルを繰り返すことで、洗い出した問題点の改善によって成果が出ているかを確かめられるためです。
これからLPO対策をしようと思っている方は、今回お伝えしたことを念頭に置くと良いでしょう。
LPO対策のコツ7選

LPO対策をするときは、次の7つのコツを押さえれば効果を高められます。
・ファーストビューを魅力的にする
・CTAボタンの配置やデザインを最適にする
・外部リンクを設置しない
・コンテンツの権威性を高める
・ページの読み込み速度を速くする
・A/Bテストを定期的に行なう
・各種デバイスに対応させる
以下では、詳しく解説します。
ファーストビューを魅力的にする
ファーストビューとは、「ランディングページのうち、ユーザーが最初に目にする部分のこと」です。
広告や検索結果からやってきた、ユーザーに立ち止まってもらえるかどうかを決める重要なパートといえるので、ユーザーを惹きつけるキャッチコピーや画像、CTAボタンが欠かせません。
ファーストビューに記す文言は広告に書かれている文言と揃えましょう。
内容を同じにすることで、じっくり読んでもらえる可能性が高まり、最終的にはコンバージョンに繋がります。
逆に、ファーストビューの文言を広告の内容と異なるものにしてしまうとユーザーは、「期待して遷移したのに、思っていたのと違う」と感じ、ランディングページから離脱してしまうでしょう。
CTAボタンの配置やデザインを最適にする
CTAボタンとは、「ユーザーをコンバージョンに導くためのボタンのこと」です。
「購入ボタン」「申し込み」「問い合わせ」は、その代表例といえるでしょう。
文字の大きさや色、配置、内容が1つ違うだけで、コンバージョン数に大きく影響します。
色々なパターンで試行錯誤してみて、ユーザーからの受けが良さそうな形にしましょう。
そうすれば、クリック率アップも見込めます。
外部リンクを設置しない
ランディングページを制作するときは、なるべく外部リンクを設置しないようにしましょう。
ページ内にリンクがあると、ほとんどの訪問ユーザーは遷移したまま戻ってきません。
LPO対策をしているが、ユーザーの離脱率(直帰率)が高くてお困りの方は、外部リンクの数を見直してみましょう。
設置しないようにすることで離脱を防ぐことできます。
コンテンツの権威性を高める
ランディングページに掲載するコンテンツは質にこだわりましょう。
なぜなら、コンテンツが客観的なデータに基づいていたりすると、ユーザーから「この会社は信頼するに値する」と思ってもらえる可能性が高まるためです。
現に、Googleは近年E-E-A-Tと呼ばれる評価基準に基づいてサイトを評価しており、記事の「専門性」「権威性」「信頼性」を重要視しています。
「どんなことを言っているか」ももちろん大切ですが、「誰が言っているか」を重視しているのです。
そのため、最近ではコンテンツに説得力を持たせるために、専門家へのインタビューなどをランディングページに掲載している方もいらっしゃいます。
ページの読み込み速度を速くする
読み込み速度が遅いランディングページほど、訪問ユーザーの離脱率(直帰率)が高い傾向にあります。
実際、2017年から2018年にGoogleが行なった調査によると、「ページの読み込み速度は、1秒から3秒になると、離脱率が32%増え、6秒になると106%、10秒かかると123%増える」と言われています。
このように、ページの読み込みが遅いと、ユーザーはコンバージョンどころか、ページを閲覧することすらせず、いなくなってしまうのです。
顧客獲得のチャンスを逃してしまわないためにも、画像を最適化するなどして対策しましょう。
A/Bテストを定期的に行なう
A/Bテストとは、「AパターンとBパターンの2つを用意して、どちらの施策の方が良いかを判断するテストのこと」です。
Webマーケティングの分野ではよく使われる手法で、ランディングページだけでなく、Webサイトや広告、バナーを最適化するのに役立ちます。
2パターンのコンテンツを用意して比較することで、ユーザーに最も刺さる要素を選択できます。
検証に少し時間がかかるのが難点ですが、比較結果をもとに効果のより高い方を選べる点で優れています。
ランディングページのクリック率やコンバージョン率を高めたいとお考えの方は、A/Bテストを実施してみてはいかがでしょうか。
各種デバイスに対応させる
LPO対策の一環として、ランディングページをPC・スマホ・タブレット、どのデバイスでも問題なく見られるようにしておきましょう。
特に、スマホ対応は重要と言えます。なぜなら、近年スマートフォンで利用する人が急増しているためです。
実際、総務省が2021年に行なった調査によると、個人のインターネット利用率は「スマートフォンが68.5%であるのに対し、パソコンの48.1%である」ことがわかっています。
このように近年は、PCだけでなくスマートフォンを始めとする頬化のデバイスからアクセスするユーザーが増えつつあるので、ランディングページを最適化させる際にも各種デバイスへ対応は欠かせません。
まとめ

LPO(Landing Page Optimization)とは、「商品やサービスに関する問い合わせや資料請求の件数(コンバージョン)を増やすために、ランディングページを顧客にとって使いやすいものに改善すること」です。
「広告の費用対効果を高精度に分析できる」「顧客満足度が高まる」といったメリットがあります。
そんなLPOは、SEO・EFOと名前や働きが少し似ているため混同されやすいですが、意味が異なります。
LPOとSEOの違う点は、「コンバージョンの増やし方」で、LPOとEFOの違う点は「改善する範囲」です。
LPOを行なう時は、まず目的の明確化とKPIの設定が必要です。
次に、現状の課題を明らかにしたうえで具体的な施策を決めます。施策を実施したら、最後に効果測定を行ないましょう。
自社の売り上げアップのためにCV率や広告の費用対効果を高めたい方は、LPO対策してみてはいかがでしょうか。
【株式会社セレクト・ワン】
東京本社:03-5953-7160

株式会社セレクト・ワンの社員によってオススメ情報を執筆している【編集チーム】です。”初心者の方にもわかりやすく”をモットーに、記事を読んだら直ぐに実践できるWEBマーケティング関連の情報を紹介しています。
また、弊社の実績や導入事例から見る・コンテンツマーケティング・SEO対策・WEB制作など、様々な最新情報やノウハウも発信していきます。