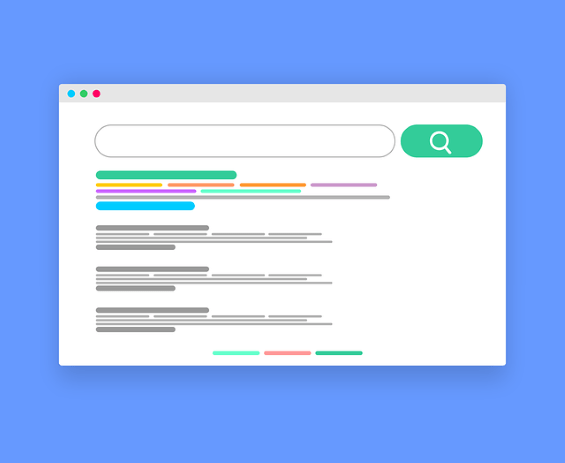お問い合わせフォームからユーザーの離脱を防ぐEFO対策とは?

WEBサイトから資料請求やお申し込みをする場合に、項目が多く入力しづらいお問い合わせフォームに遭遇した経験は、皆さんもあると思います。
サイトに訪問して、その会社のサービス内容や料金形態を気に入って、お問い合わせフォームまで到達したにもかかわらず、約70パーセントのユーザーは、資料請求やお申し込みを行うこともなく途中で離脱していると言われています。
今回は、WEBサイトのお問い合わせフォームからユーザーの離脱を防ぐ【EFO対策】について紹介をさせていただきます。
EFO対策とは?

SEOとは、【検索エンジン最適化・Search Engine Optimization】の頭文字を取った略称のことで、自社のサイトを特定のキーワードで検索した場合に、検索順位で上位に表示させる対策のことを意味しています。
もう少し詳しく説明をすると、良質な被リンクを集めるSEO外部施策と、ユーザーに有益なコンテンツを提供しWEBサイトを最適化(SEO内部施策)して、検索結果の順位を上げることをSEO対策と呼んでいます。
一方、お問い合わせフォームからユーザーの離脱を防ぐ対策は、EFOと言われています。
EFOとは、【Entry Form Optimization】の略称のことで、資料請求やお問い合わせフォームの離脱ポイントを見つけて最適化することで、ユーザーの入力率を向上させて離脱率を下げるための対策のことを言います。
また、EFOの別名では、【入力フォーム最適化】と呼ばれることもありますが、お問い合わせフォームの通過率を上げるための対策とも言えるでしょう。
多くのユーザーが途中で入力作業をあきらめてしまう

ここでは、お問い合わせフォームや資料請求フォームの途中から、ユーザーが入力作業をあきらめて離脱してしまう原因とその改善策について紹介させていただきます。
お問い合わせフォームの項目のわかりにくさやエラー表示による再入力など、ストレスが掛かることが発生すれば、ほとんどのユーザーは途中で入力作業をあきらめてしまいます。
特に入力をするのに手間が掛かったり、やり直しが発生するなどの面倒くさい作業は、ユーザーがストレスを感じますので、お問い合わせフォームを離脱する大きな原因になります。
これらの改善策として、ユーザーが行う入力作業の手間を軽減させて、お問い合わせフォームの利便性をあげることが必要です。
これまで感じていた、入力時のストレスを軽減できる仕様に、お問い合わせフォーム自体を最適化することで、ユーザーのストレスや負担を減らして離脱を防ぐことができます。
ユーザーがお問い合わせフォームから離脱する原因

1.入力する項目や内容が多く、お問い合わせフォームが複雑に感じる。
2.入力項目に対するアシスト機能がお問い合わせフォームに無く、入力する項目の数が多い。
3.入力の途中でエラーが発生して、お問い合わせフォームがリセットされてしまう。
4.入力必須の項目がどれに該当するのか、表示がわかりにくい。
5.入力するテキストに全角入力や半角入力の指定がある。
6.入力項目の枠(縦・横)自体が小さく、お問い合わせフォームが入力しづらい。
7.具体的な記載例が無いので、入力する内容がわかりにくく、記載するテキストの量が多い。
8.入力すること自体にストレスを感じるデザインになっている。
お問い合わせフォームの改善策 8選

入力項目を簡潔にまとめて情報やテキストの数を減らす
ユーザーに入力してもらう情報やテキストの数を極力少なくして、必要最低限の労務で済むようにまとめる。
入力項目に自動入力機能(補助機能)を付ける
住所などは、自動入力機能(補助のシステム)を導入して、お問い合わせフォーム側でユーザーの入力作業をサポートする。
リセットされる前にその場でエラー表示をさせる
入力のエラーは、すべての入力作業が完了した最後に表示させるのではなく、入力をした時点でエラー表示をさせてユーザーへ告知する。
入力必須の項目のアイコンは画像などを利用して目立たせる
ユーザーはそこだけの必要最低限の入力作業で済むので、入力必須の項目はあえて目立たせる表示を付ける。
全角や半角は自動変換機能(補助機能)を付ける
全角や半角は、自動変換機能(補助のシステム)を導入して、お問い合わせフォーム側でユーザーの入力作業をサポートする。
入力項目の枠(縦・横)は大きめにする
視覚性の向上やスマホ入力の誤操作防止にもなるので、お問い合わせフォームに大きな枠(縦・横)のデザインを採用する。
入力事例を記載する
入力作業のミスやエラーの防止につながるので、ユーザーがわかりやすいように具体的な記載例を表示しておく。
入力完了までのステータス(進捗状況)を表示させる
入力作業があとどのくらいで完了するか?の目安として、ユーザーに安心感を与えるためのステータス(現状はどこまでの入力が完了しているのか)を表示させる。
EFO対策はツールを活用する

ここまでの解説で、EFO対策がどのようなものか理解いただけたと思います。
そんな、EFO対策をスムーズに行うためには、ツールを活用することをオススメしています。EFOツールには大きく3つのタイプが存在して、主な機能は2つあります。
EFOツールのタイプ
導入がお手軽なツール
タグを埋め込むだけで、簡単にツールが設置できるもの
カスタマイズが容易なツール
レイアウトの変更や文字の変更などが簡単にできるもの
スマートフォンに最適なツール
スマートフォンの画面に特化して最適化されたもの
EFOツールの機能
入力支援機能
ユーザーがフォームに入力する際に、その作業をサポートするもの
レポート機能
入力フォームに訪問したユーザー数や離脱した数値などの割合を表すもの
上記以外にも、利用中のカートシステムと連携できるものや、2つのパターンを比較するABテストができる機能が備わったものが存在します。
効率的に入力フォームを改善できるEFOツールは、自社の現状に合ったものを選定することが必要です。
おわりに

今回は、WEBサイトのお問い合わせフォームからユーザーの離脱を防ぐ、【EFO対策】について紹介をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
SEO対策で、検索順位を上げてWEBサイトへの集客を行っていても、お問い合わせフォームが原因で多くのユーザーが入力をあきらめてしまっては、コンバージョンにはつながっていきません。
事前に知っておきたいことは、流入数の多いサイトであっても、お問い合わせフォームまでの導線が確保されていない場合は、集客の効果が限定されてしまうということです。
EFO対策を導入する前は、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを活用して、WEBサイト内部の導線や問題をあらかじめ修正しておかなければなりません。
また、WEBサイトを閲覧したユーザーが途中で離脱をしていないか、お問い合わせフォームまでは確実に到達しているか、などユーザーの動向まで含めて確認することも必要です。
この記事をご覧になった方は、ユーザーに途中であきらめられることがない、最適なお問い合わせフォームを目指して【EFO対策】に取り組んでみてはいかがでしょうか。
【株式会社セレクト・ワン】
東京本社:03-5953-7160

株式会社セレクト・ワンの社員によってオススメ情報を執筆している【編集チーム】です。”初心者の方にもわかりやすく”をモットーに、記事を読んだら直ぐに実践できるWEBマーケティング関連の情報を紹介しています。
また、弊社の実績や導入事例から見る・コンテンツマーケティング・SEO対策・WEB制作など、様々な最新情報やノウハウも発信していきます。